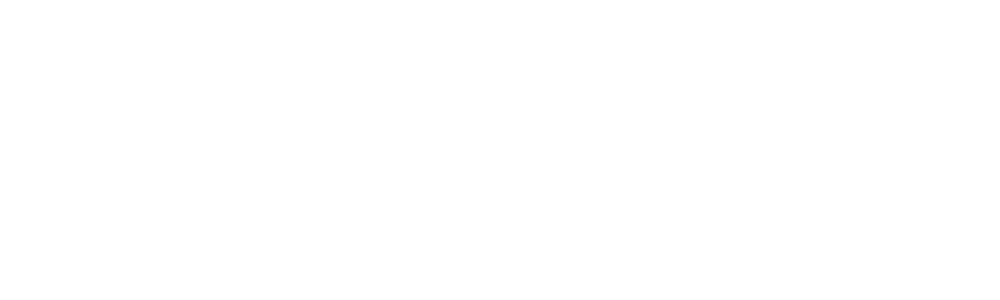年度初めが慌ただしいのは、分かっていたつもりだった。けれど、やっぱり毎晩のように授業の準備に追われてしまう。今日も、気がつけばこの時間。「え?定時やろ!」なんてツッコミが聞こえてきそうだけれど、まあ、これが現実だ。
でも不思議なことに、学生の顔を思い浮かべながら授業のプランを練るのは、案外楽しい作業だったりする。どんな反応をしてくれるだろう、何に引っかかり、何に笑ってくれるだろうか――そんなことを考える時間が、僕の中ではすでに授業の一部になっている。
これはワークショップでも、講義でも、演習でも、同じことだ。
演劇家として、僕はいつもオーディエンスを意識する。目の前の誰かにどう届くか。どう響くか。つまりは、「受け手の立場で考える」こと。それを自然に考えるようになったのは、やっぱり演劇という世界で鍛えられてきたからだと思う。この視点には、大きな教育的価値があると信じている。だからこそ、これから教える立場につく人たちに、どうしても伝えたい。
ただ教えるのではなく、「どう届くか」。
学びを誰かと共有する時間は、実に豊かだ。新しいことに気づく瞬間。思わず「おもしろい!」と声が漏れる瞬間。つい笑ってしまうやりとり。そんな時間のひとつひとつに、学びの本質があるんじゃないかと思っている。
僕が今こうして教壇に立っている原点は、1994年のアメリカ留学にある。そこで出会った、とある授業。後に僕の師となる先生が教えていたそのクラスに、心を奪われた。「大学で教えたい」――その憧れが、いつの間にか夢になった。そして今、アメリカと日本、ふたつの国でその夢を叶えることができた。それはひとえに、授業をすることが楽しくて、ただ楽しくて、コツコツと歩みを止めなかったからだと思っている。
さて、明日もどんな学びをつくろうか。